革靴は修理やリペアを行ってあげる事でスニーカーなどと違って永き続ける事ができるのが魅力です。いい革靴を購入し修理や手入れを適切に行う事で一生履けるなんて言われており、とてもサスティナブルなアイテムでもあります。
ところが、修理やリペアのタイミングは履く頻度や履き方によって人それぞれタイミングは異なってきます。修理を行うタイミングが遅すぎると、ソールが摩耗しすぎて修理が出来なくなってしまう何て事もあり得ます。
そこで今回は革靴の修理やリペアをするタイミングや見るべき場所を紹介していこうと思います。
ちょうど私の所有しているユニオンインペリアルの革靴のソール部分やヒール部分が摩耗してきていたので、修理のタイミングや修理の方法も含めて紹介していきます。
革靴を修理するタイミングについて
革靴の修理やリペアは基本的に地面に接する面(ソール)を行う事がほとんどです。革靴のソールのどこを見れば修理のタイミングが分かるかを写真を基に説明していきます。
かかとのトップリフト部分

革靴のヒール部分(かかと部分)をトップリフトと呼びます。
修理に出すタイミングとしては、かかとの磨耗がトップリフトのゴム上部の革部分(積上)に達する前に修理に出すようにしていただく事をお勧めします。上の写真の赤線を超えてしまうとトップリフト全体を交換になってしまい費用が高くなってしまうので、赤線が超えないギリギリのタイミングで修理に持っていくといいと思います。

私の所有しているユニオンインペリアルのダブルモンクは向かって左側が摩耗し削れており、赤線ギリギリまで達しているので交換すべきタイミングだと思います。
トゥ(つま先)部分

こちらは革靴のつま先部分(トゥ)の画像になっており、購入後にラバーを張ったのでこんな使用になっています。
革靴のつま先は削れやすく上の写真の赤線を超えてしまっているとそもそも修理が出来なくなってしまうので、赤線まで摩耗する前にオールソール(ソール全体の張替)かラバーのみ張替を行うようにして下さい。
つま先は特に削れやすいので、購入後にトゥスチールなど付けると修理までの期間を延ばす事が出来るので、気になる方は試してみて下さい。
実際にソールの修理を行ったらどうなった!?

左側が修理前で右が修理後の写真となっております。革靴のソールに張っていたラバーの交換とトップリフト(ゴム部分)の交換を行いました。

ヒールの磨耗がトップリフトのゴムの上部でヒールリフトまで摩耗していなかったのでトップリフトの交換のみで済みました。

トップリフトの交換の際にヒール部分は「ラバー+レザー」で仕上げてもらい飾り釘を打ってもらいました。ちょっと見栄えが良くなった気がしませんか?笑

まとめ
革靴のソールの修理やリペアするタイミングについて言及させていただきました。
ラバーが削れてきた際にはラバーだけ交換することでオールソールせずに永く履くことができるので、私は仕事用の革靴は基本的にレザーソールにラバーを張っています。
革靴は適度に磨いてあげる事や修理・リペアなどを行うことで長く履き込むことができるすばらしいアイテムだと思います。修理やリペアの正しいタイミングを計る参考になればと思います。
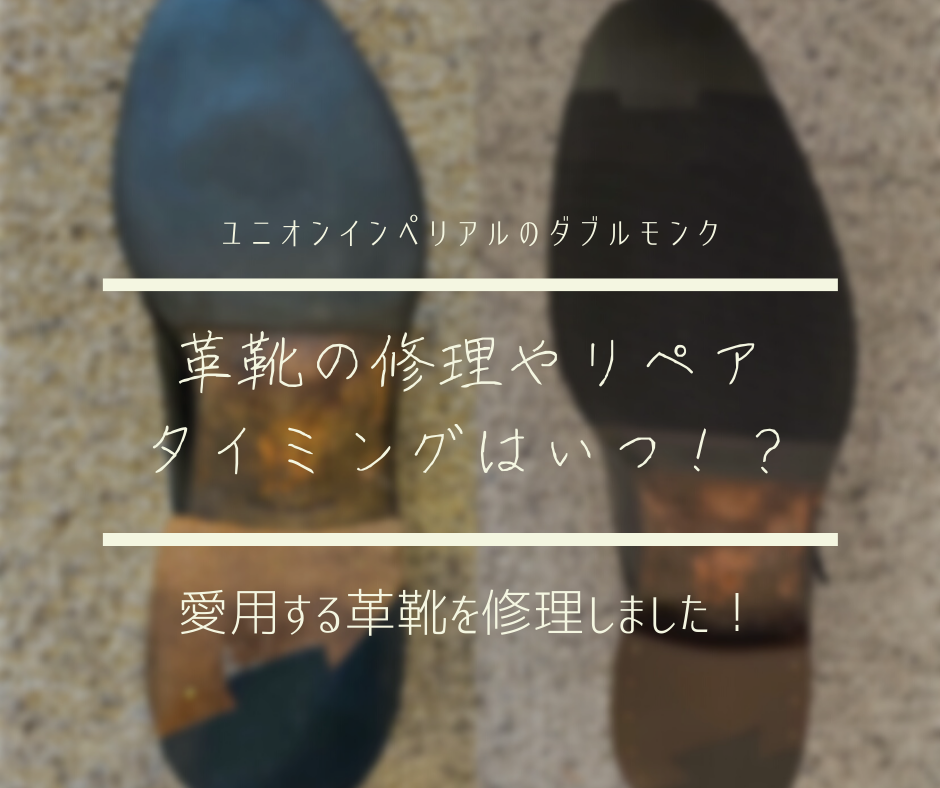
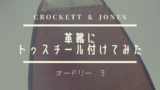

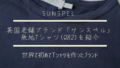
コメント